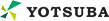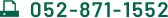技術コラム TECHNICAL COLUMN
設計者必見!ステンレス切削加工を考慮した設計のポイント
- ステンレス
ステンレス部品の設計を行う際、加工しやすい設計を意識することで、コストダウンや品質向上に繋がります。この記事では、ステンレス加工を熟知したプロの視点から、設計段階で考慮すべきポイントを解説します。加工業者とのスムーズなやり取りや、後工程でのトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
加工性を考慮した設計の重要性
部品の設計は、その後の製造プロセスに大きな影響を与えます。特に、難削材として知られるステンレスの場合、設計のわずかな違いが、加工時間や工具の摩耗、ひいてはコストに直結します。加工性を考慮せずに設計された部品は、製造が困難になったり、要求される精度が出せなかったりするリスクがあります。例えば、鋭利な角や深すぎる溝、非常に薄い壁などは、加工硬化や工具への負担を増大させ、結果として製造コストを押し上げることになります。
設計段階で加工業者と密に連携し、彼らの専門知識を活かすことで、無駄のない効率的な製造が可能になります。これにより、最終的な製品の品質を高めつつ、トータルコストを削減できるのです。
R(アール)の適切な設定
部品に角を設ける際、R(アール、角の丸み)のサイズは非常に重要です。切削加工では、工具の先端形状によって加工できるRの最小サイズが異なります。特に、内側の角は工具の径よりも小さなRを付けることができません。無理に小さなRを要求すると、細い工具が必要となり、工具の折損やびびり振動の原因になります。
一般的に、切削加工では工具径の半分以上のRを設けるのが望ましいとされています。可能な限り大きなRを設けることで、より汎用的な工具を使用でき、加工時間を短縮し、コストを抑えることができます。また、Rのサイズが大きければ、切削による熱の集中を緩和し、加工面の仕上がりも向上します。
穴あけ加工の注意点
ステンレスの穴あけ加工は、加工硬化の影響を受けやすいため、特に注意が必要です。加工硬化により穴の底が硬くなると、次の工程でドリルが食い込まず、工具が滑ってしまい、穴の精度が低下したり、工具が破損したりする可能性があります。
この問題を避けるためには、穴の深さを適切に設定することが重要です。穴の深さがドリルの直径の3倍から5倍を超える場合、切りくずの排出が困難になり、工具への負担が増します。さらに深い穴を必要とする場合は、段階的にドリル径を変えたり、深穴用の専用工具を使用したりするなどの工夫が必要です。また、貫通穴の出口ではバリが発生しやすいため、後工程でのバリ取り作業を考慮した設計も求められます。
薄肉形状の設計
ステンレスは粘り強いため、薄い壁やリブを加工する際には、びびり振動が発生しやすくなります。このびびり振動は、加工面の仕上がりを悪化させるだけでなく、工具の寿命を著しく縮める原因となります。また、薄い部分は熱を逃がしにくく、加工熱による変形も起こりやすくなります。
これを防ぐためには、可能な限り壁厚を確保することが重要です。もし薄肉部分が必要な場合は、リブ(補強材)を追加したり、複数の工程に分けて少しずつ加工したりするなど、加工業者との連携が不可欠です。また、薄い部分が加工途中で変形しないように、適切なクランプ(固定)方法を考慮した設計も有効です。
まとめ
ステンレス部品の設計は、その後の製造プロセス全体を左右する重要なステップです。加工硬化や熱伝導率の低さといったステンレス特有の難しさを理解し、設計段階から加工性を意識することで、高品質な製品を効率よく製造できます。
本記事で解説したRの設定、穴あけ、薄肉形状の設計ポイントは、いずれも加工コストと品質に直接影響します。これらの点を設計段階から考慮することで、加工業者とのコミュニケーションが円滑になり、試作回数の削減にも繋がります。設計者と加工業者が互いの知識を共有し、協力することで、最高の製品を生み出すことができるのです。